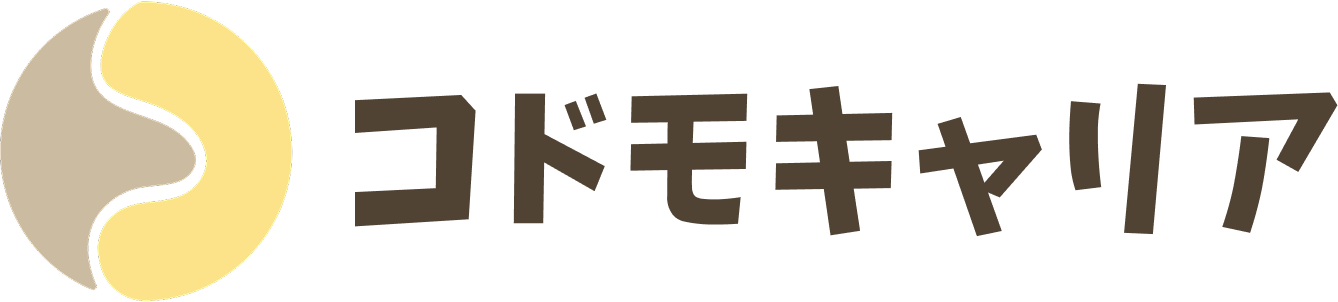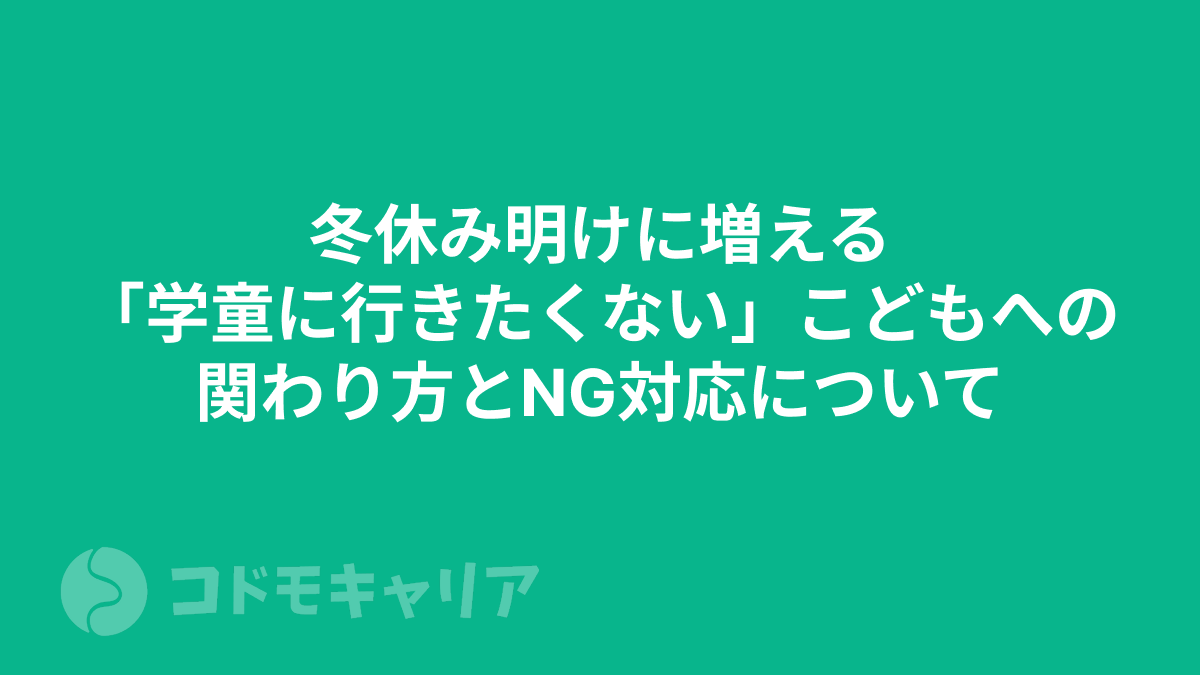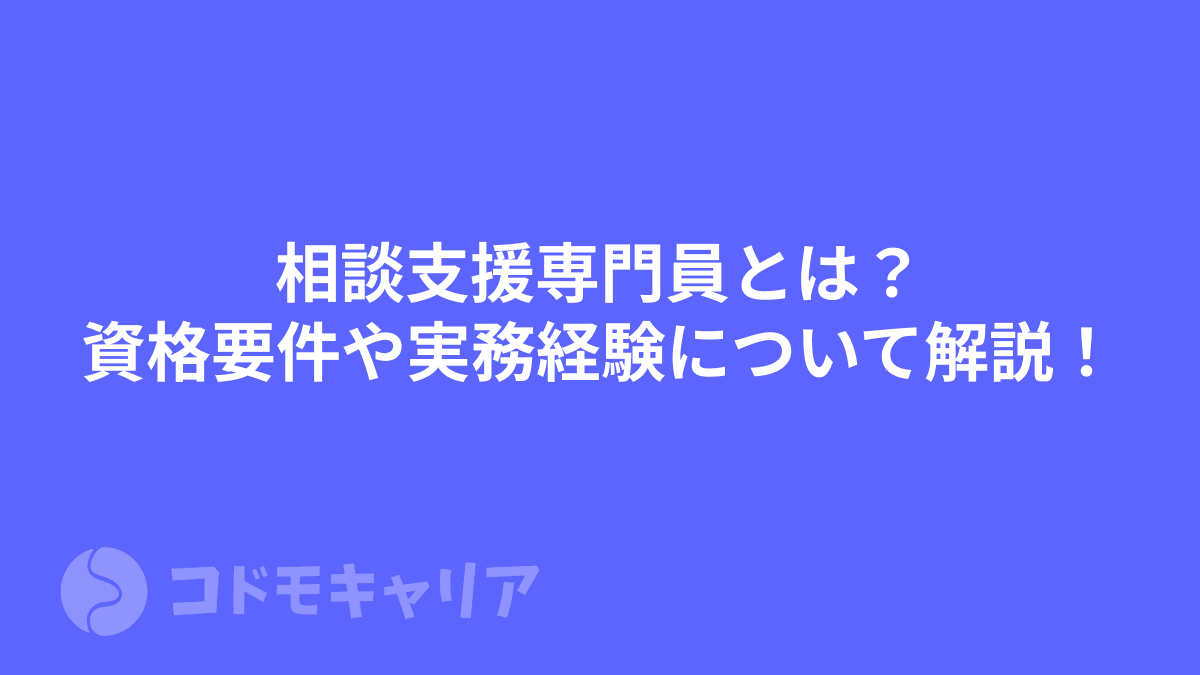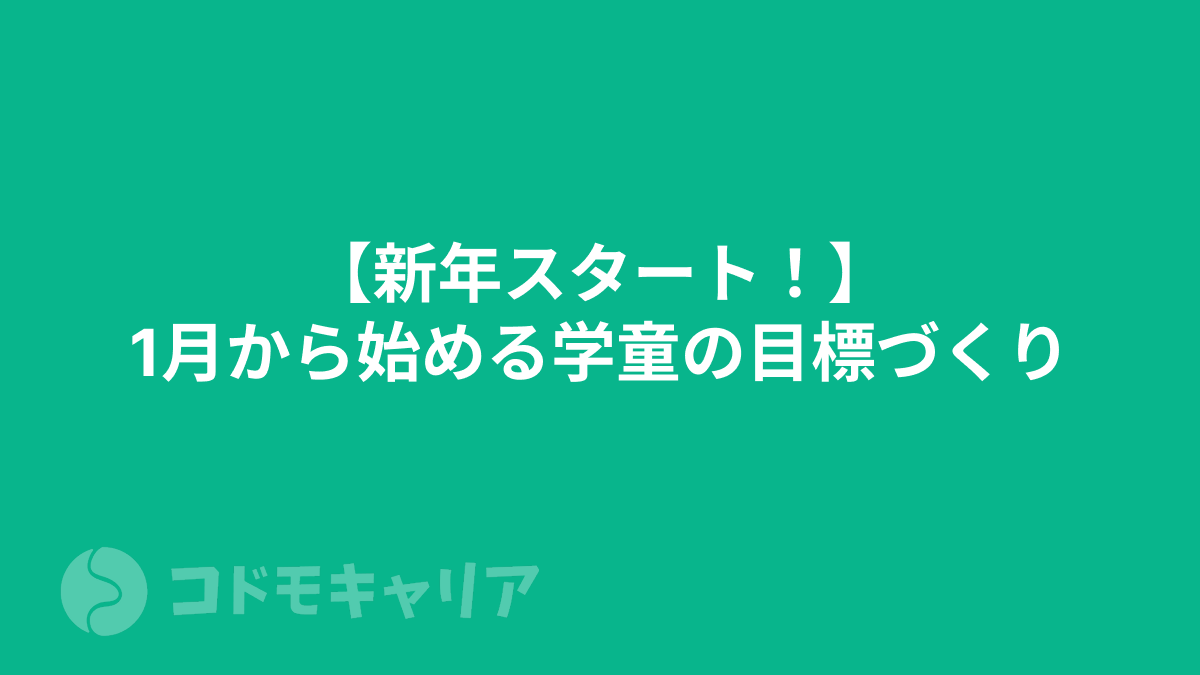タグで絞り込む
キーワードから探す
【こどもの権利を知ろう】学童でこどもの声をきく仕組みづくり

学童
公立学童
民間学童
学童経営
毎日多くのこどもたちが集まる学童保育所は、学校でも家でもない「第三の居場所」として、安心・安全に放課後の時間を過ごせることはもちろん、「自分の声が大人に届く場所であること」つまり「こどもの権利が尊重されている環境であること」がとても重要です。
「今日はこれがしたい」や「この学童のルールは少し変だと思う」など、様々な意見や小さな呟きの一つひとつが、こどもたちの大切な「意見」です。それらの声を受け止め、日々の運営や関わりに反映していくことが、こどもの権利を守り、主体性を育む第一歩になります。
本コラムでは「こどもの権利」についてまとめた上で、学童でできる「こどもの声をきく仕組みづくり」の例をご紹介します。
1. 「こどもの権利」と「意見表明権」とは?
「こどもの権利と聞いても、イマイチぴんとこない」
「言葉自体に、あまり聞き馴染みがない」
「なんとなく分かるけど、詳しくは知らない」
…もしかしたら、そんな方もいるかもしれません。
しかし1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」を日本も1994年に批准しており、2023年には「こども基本法」も施行されたことで、「こどもの権利を守る関わり」がこれまで以上に強く求められているのが現状です。学童保育所もまた、こどもたちの日常生活に大きく関わる機関として、こどもの権利を守る関わりを実践していく重要な存在です。
なお、「子どもの権利条約」には、すべてのこどもがもつ4つの基本的な権利が以下のように示されています。
1. 生きる権利(生命・生存・発達の権利)
2. 育つ権利(教育や愛情を受ける権利)
3. 守られる権利(暴力や搾取から守られる権利)
4. 参加する権利(意見を表明し、尊重される権利)
この4つの基本権利は全て等しく重要なのですが、学童保育所で実践していくことが特に期待されているのが「参加する権利」いわゆる「意見表明権」です。これは、こどもたちが自分の考えを自由に発言し、それらが真剣かつ丁寧に受け止められる権利のことをいい、学童内のイベントや遊び、ルールについてこどもたちが意見できるかどうかが大きなポイントになってきます。

2. こどもの声をきく仕組みづくりについて
「意見表明権」を大切にした関わりを考えるには、「こどもたちの声をきく仕組みづくり」が重要になってきます。
「こどもの意見をきく」というと、言葉として発された意見を耳から聞き取る…というニュアンスが感じられるかもしれませせんが、必ずしもこどもたちの意見・声は音として表現されません。「恥ずかしい」や「怖い」、「うまく言葉が出てこない」など様々な理由で声にすることはできずとも、行動や表情によって意見を表明する子がいたり、文字で意見を伝えてくれる子がいたりいます。
実は「子どもの権利条約」の英語原文でも、こどもの意見は「Opinion(意見)」ではなく「View(見ること)」と訳されており、完成された言葉・声として耳から拾い上げられないような、小さなぼんやりとした視点・感情・思いのようなものも、立派な「こどもの意見」と捉える必要があります。
こどもたち一人ひとりの意見や声なき声を、「耳」だけでなく「目」と「心」も使いながら、拾い上げているような多様な仕組みを学童保育所でもつくっていくことが大切なのです。学童保育所における「こどもの声をきく仕組みづくり」の例を今回は3つ紹介します。
①「こども会議」
こども会議とは、学童のルールやイベント内容などについて、こども自身が話し合って決める仕組みです。自分たちに関わることは自分たちで決められるという「参加する権利=意見を表明する権利」に直結する、非常に有効な取り組みといわれています。全てを大人に決められるのではなく、自分ごととして物事を決めていく体験は、主体性と自己選択の力を育ててくれます。
毎日実施するのは難しいですが、何かイベントを控えているときやトラブルが起きたときなどに、積極的に実施できると良いでしょう。
このとき、注意しなければいけないのは「参加したくない」や「意見を言いたくない」という子の気持ちも尊重をするべきだということです。こどもの声をきくことに躍起になってしまい、強い圧をかけながら意見を求めることはこどもにストレスを与えることになり、こどもの権利を守ることに繋がりません。あくまで「言いたい」と思っている子の意見を拾い上げる場である、という意識を忘れないようにしましょう。
● こども会議の流れ(例)
(1) テーマを決める。
→例:「冬休みの行事を考えよう」「新しい遊びルールをつくろう」など。
(2) ルールを確認する。
→例:「話すときは挙手をする」「人の話は遮らず最後まで聞く」など。
(3) 話し合いスタート。
→職員はファシリテーターとして、意見が偏らないよう支援します。言いたそうだけど言えない子のサポート・代弁なども必要に応じて実施します。口頭の発表だけでなく、筆記道具や付箋、絵カードを活用するなどして、全員が表現しやすい方法を取り入れます。
(4) 決定事項を掲示する。
→「みんなで決めたこと」が目に見える形にまとめて掲示すると、責任感と達成感がより育ちます。また、こども会議に参加できなかった(しなかった)子にも内容を共有することで、不満感を抱かせたり伝達ミスが起きたりすることを防げます。
②「こども主体のイベント企画運営」
こどもまつりや誕生会、お楽しみ会など、学童では毎月様々な行事が開かれています。それらのイベントの企画運営を職員が主導するのではなく、こどもたち自身が関わっていくことで、計画力(=自分たちで段取りを立て、物事を進める力)や協働力(=友達の意見と折り合いをつけながら協力して取り組む力)が育まれ、大きな達成感を得られます。
また、自分の声が話し合いを経て実際にイベントとして形になるという経験は、「自分も社会の一員だ」という実感や「自分の声には意味がある」という自信にもつながります。普段の学童行事が「大人が決めた強制的なイベント」というやらされるものから、「自分たちで作り上げた主体的なイベント」という積極的なものに変わることで、充実度や楽しさが倍増するのです。
● 実践の流れ
(1) どのようなイベントをやるかこども会議で決める。
→どんなイベントをやりたいかざっくばらんに意見出しをした後は、「イベントで具体的に何をするか」というこども会議で話し合いをします。
(2) 役割分担を自分たちで決める。
→店番、司会、ポスターづくり、景品係など、それぞれの「やりたい」や「好き」に応じた役割を決めて担当します。
(3) 準備から当日運営までこどもたち任せる。
→大人は安全面の見守りに徹し、口を出しすぎないことがポイントです。なお、大人の意見をみんなに伝える時間をとり、予算や注意事項などを最低限伝えることは必要になるかもしれません。
(4) イベントのふりかえりを一緒に行う。
→「うまくいったこと」や「大変だったこと」を共有し、次への改善につなげます。
③ 「こどもの意見箱」
話すのが苦手な子、みんなの前では意見を言えない子、こども会議やイベント準備に参加できなかった子…。
そんなこどもたちの声を拾うためにおすすめなのが「こどもの意見箱(ポスト)」です。
これは、こどもたちが自分の意見を紙に書いて投函するだけで、安心して大人に気持ちを伝えられる手軽な仕組みです。いつでも誰でも意見を書けるという点でフェアであたたかい仕組みともいえます。
● 運用のポイント
(1) 匿名でも書けるようにする。
→安心して本音を出せる環境をつくる。
(2) 定期的に開封・共有する。
→週1回などのルールを決めて、職員会議やこども会議で内容を確認します。
(3) どんな声も無視せず、返事をする。
→全ての意見に「意見を伝えてくれたことへの感謝」と返事を伝えましょう。できれば手紙のように返事を書いて掲示しておけると、質問者・意見の提案者以外にも閲覧することが出来るようになり、理解が深まります。
仮に実現できない内容でも、「今は〜という理由で難しいけど、検討するね」と説明や返答を掲示することで、こどもたちとの信頼関係が深まります。
3. 声をきく仕組みだけ作っても意味がない!?
上記のような仕組みづくりは非常に有効で、是非施設運営に取り入れていただきたいものですが、どんな仕組みも形だけでは意味がありません。本当に大切なのは、「こどもの声をきく姿勢」が大人一人ひとりに根づくことです。
こどもたちとの日々の会話に「どう思う?」などの問いかけを積極的に入れてみたり、行事やトラブルの後に一方的な意見や感想の押し付けではなく「どう感じた?」とこどもの素直な声に耳を傾けたり、表情・遊び方・距離感など言葉以外のサインにも目を向けたりしていく意識が重要です。
また、スタッフ同士が「こどもの声の拾い方」や「声をきく場面での工夫」を共有し合うことも、学童保育所全体の文化をつくる上で欠かせません。チームとして「こどもの権利を守る」という共通認識をしっかりと持っていくことで、「こどもの声をきく仕組みづくり」がより効果的に機能を果たしていくのです。
まとめ
こどもの意見は「わがまま」と簡単に無視して良いものではありません。
そして、こどもの声をきくことは、単なるヒアリング活動ではありません。
大人とこどもという垣根を超えて、「私」は同じ人間である「あなた」の存在を大切に思っているという意思表示をすることが、こどもの権利を守り、こどもの意見を拾い上げるということです。
日々のあたたかい関わりや、こども会議での話し合い、こども主体のイベント作りに意見箱の活用…そのどれもが、こどもたちに「学童は自分たちにとって心地よい居場所」や「こどもである自分にも出来ることがある」と感じさせてくれます。
大人が一方的にこどもたちを守ろうと物事を決めていくのではなく、こどもたちとともに考え、ともに決めていく。それが、これから学童保育所が果たすべき「こどもの権利を守る場所としての役割」といえるでしょう。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。