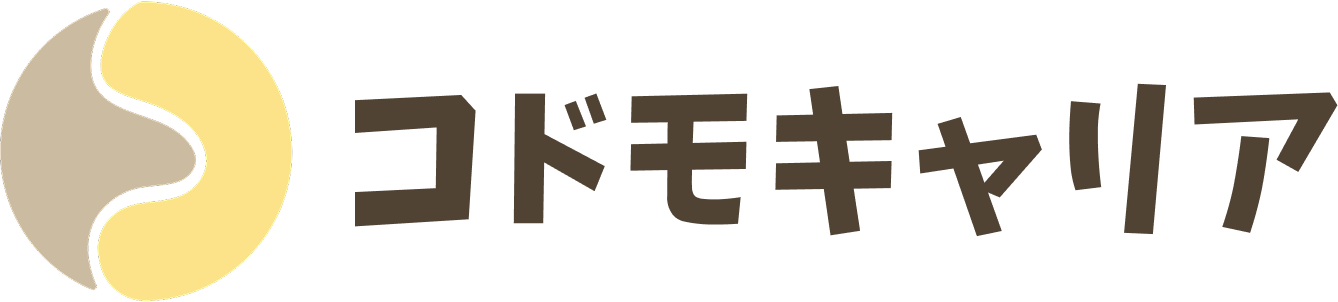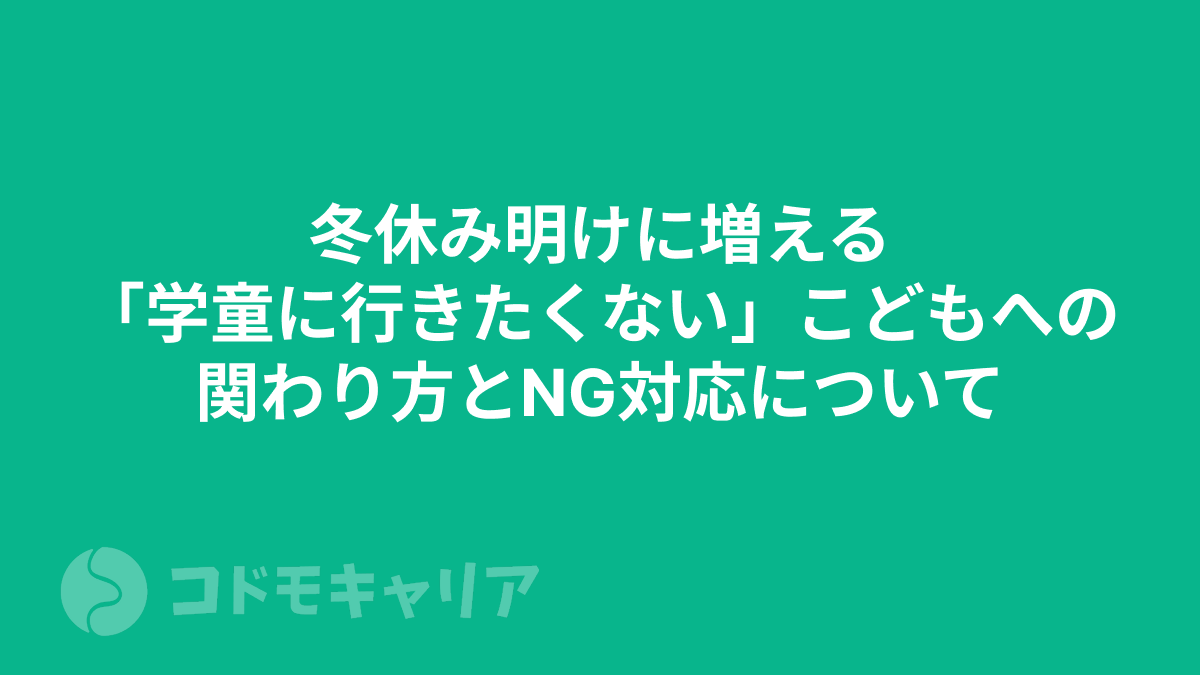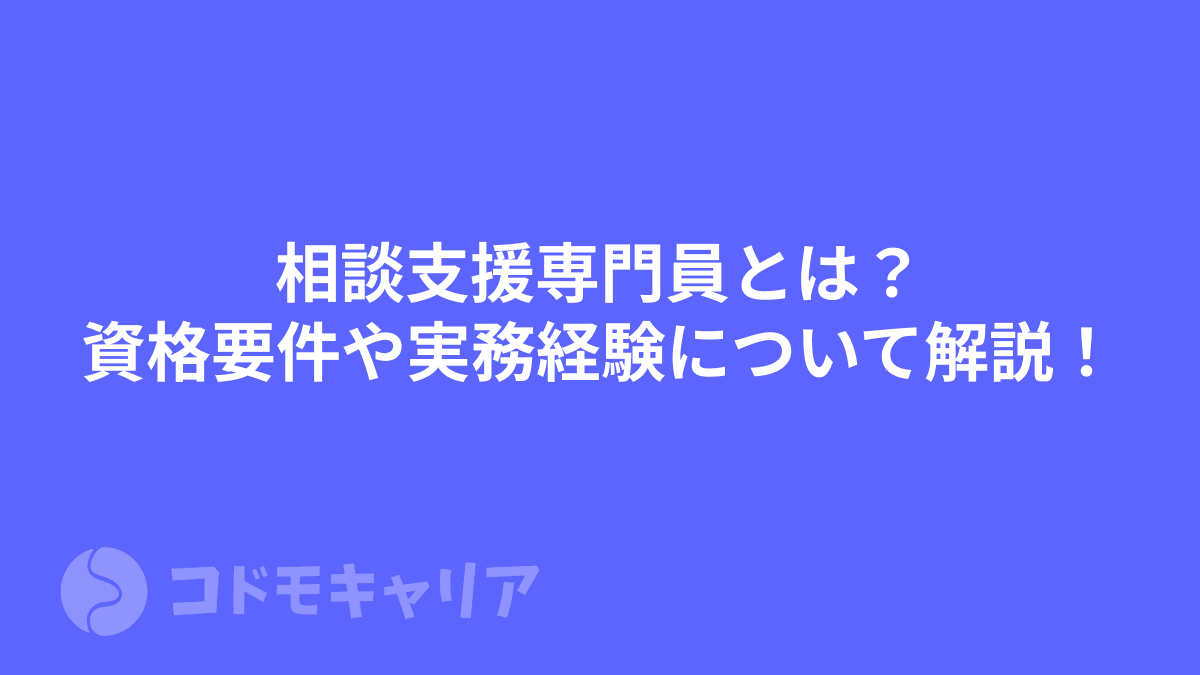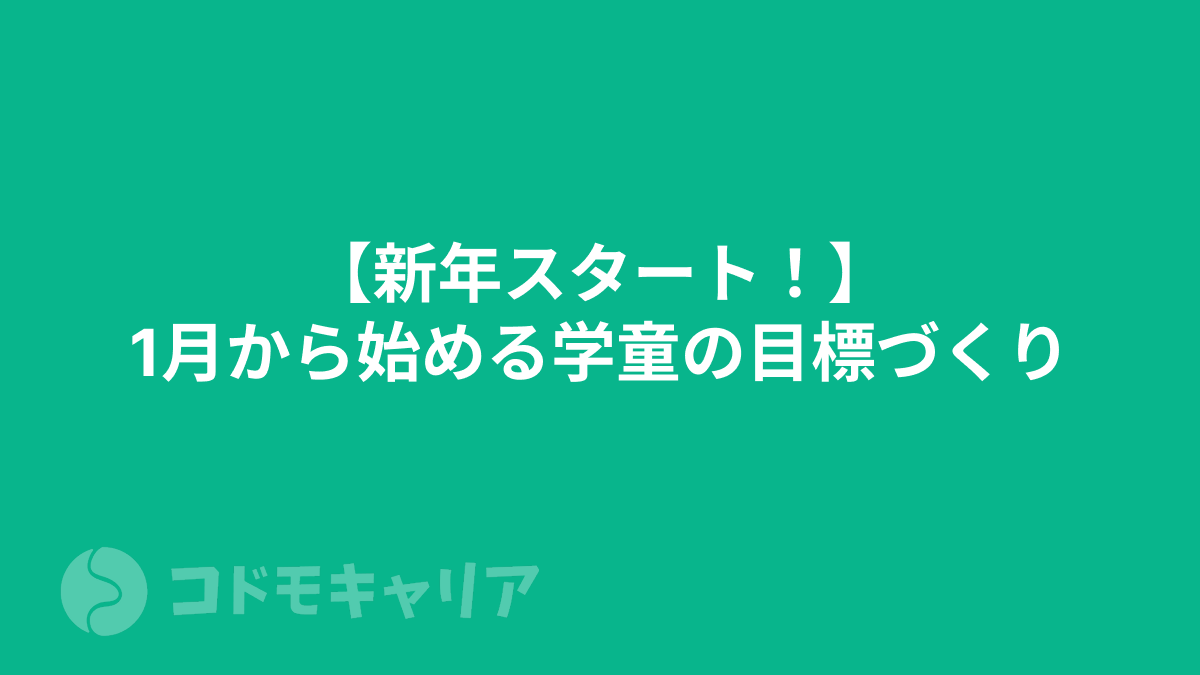タグで絞り込む
キーワードから探す
学童の「指定管理者制度」とは?運営法人はどうやって決まる?
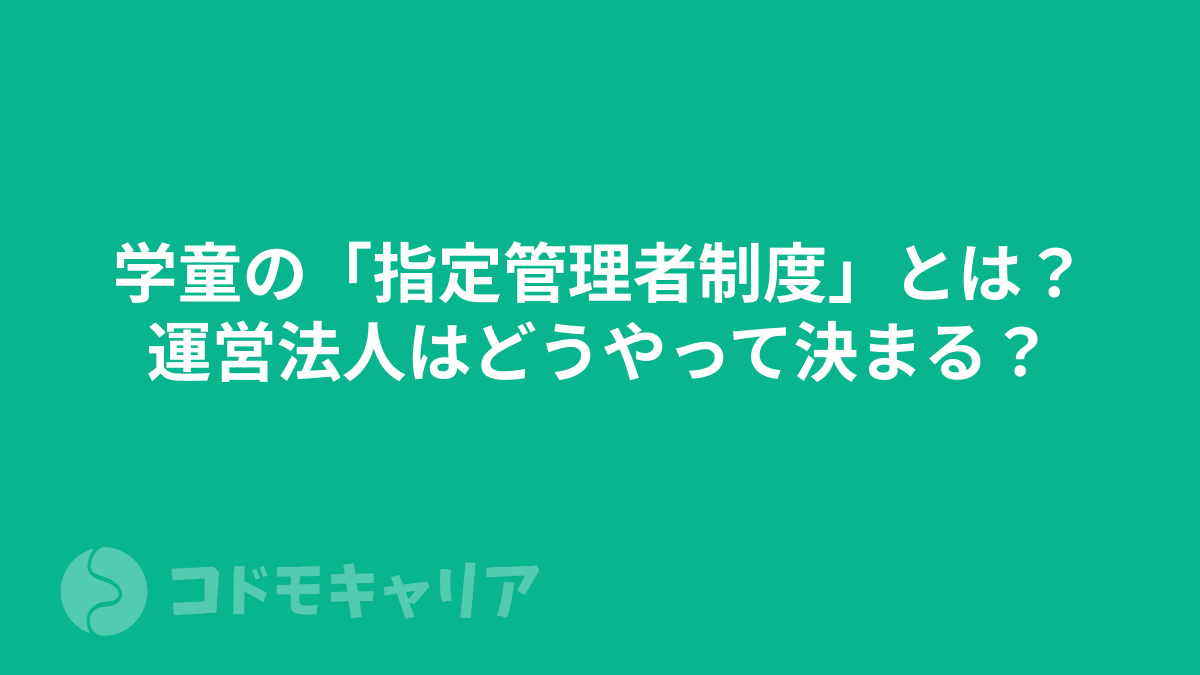
学童
実践事例
公立学童
民間学童
学童経営
放課後の時間に、こどもたちが安心して過ごすことのできる学童保育所。多くの保護者にとってはこどもを預けられる大切な居場所であり、こどもたちにとっては思う存分に遊んだり宿題をしたりして過ごすことができる第二の家のような空間です。
そんな学童保育所ですが「誰によって、どのような仕組みで運営されているのか」を知る機会は意外と少ないのではないでしょうか。
実は、学童保育所には自治体が直接運営するところ(=公設公営学童保育所)もあれば、NPO法人や社会福祉法人などの外部団体・企業が担っている場合(=公設民営学童保育所) もあります。その「外部に運営を任せる仕組み」の一つが、今回のテーマである 「指定管理者制度」 です。

名前だけ聞くとちょっと堅苦しい印象を受けますが、要するに「自治体が管理している施設を、民間の法人や団体に任せる仕組み」のことをいいます。学童保育所だけでなく、地域に根差した施設である公民館や体育館、図書館などでもこの制度は導入されています。
今回は、学童における指定管理者制度について「一体どのように運営者が決まるのか」や「制度のメリット・デメリット」という点に触れながら、分かりやすく解説していきます。
1. 指定管理者制度ってなに?
指定管理者制度とは、2003年にスタートした制度で、自治体が設置した公共施設の管理運営を民間の法人や団体に委ねることができる仕組みです。従来は「管理委託制度」と呼ばれ、委託先は社会福祉法人や自治体の外郭団体に限られていました。
しかし、2003年にこの制度ができたことで、NPO法人や株式会社などのより幅広い団体が応募できるようになり、公共施設の運営に多様な形態のプレイヤーが関われるようになりました。
学童保育所のケースに当てはめると、「施設は地域の自治体が持っているけれど、実際にこどもたちを受け入れて日々の運営をしているのは指定された法人や団体」という形になります。つまり、建物や制度の枠組みは自治体が準備し、日々の運営を民間法人や団体が担うという分担構造です。
このとき、運営を任される法人や団体を「指定管理者」と呼びます。「●●市〇〇学童保育所」などという名前で通っているがために、自治体が直接運営している公設学童だと思っていたとしても、その裏側では「●●市からの指定管理者である△△という事業者が運営している学童保育所」という仕組みになっている場合があるのです。
2. 指定管理者はどうやって決まるの?
それでは、肝心の「誰が運営するのか(=指定管理者)」はどう決まるのでしょうか。基本的には、自治体が公募を行い、応募してきた団体の中から選定委員会が審査して決定することになるのですが、この流れをもう少し詳しく見てみましょう。
① 自治体が指定管理者の募集を告知する。
「●●市〇〇学童クラブの指定管理者を募集します」という形で、対象施設・応募条件・必要な運営体制などを自治体が公表します。各自治体のHPや市報などで情報公開されることが多いです。
② 法人・団体が応募する。
指定管理者として運営を希望する法人や団体は、自治体からの指示に従って、こどもへの支援方針や人員配置計画、運営の工夫、財務状況などをまとめた提案書を提出します。ただし、希望すれば誰でも応募ができるというわけではなく、募集要件を満たした法人・団体のみが申請可能な場合が殆どです。例えば、過去の運営実績や従業員数などが必要条件とされる場合があります。
③ 選定委員会で審査される。
学識経験者や自治体関係者で構成される委員会が、提出書類やプレゼンをもとに審査します。「こどもたちの安全を守れるか」や「公設の学童にはないような独自のプログラムを提供できるか」、「継続的に運営することができるか」や「地域との連携をどう考えているか」などが評価のポイントになるようです。
④ 議会の議決を経て正式に決定する。
最終的に議会で承認され、指定管理者が決まります。契約期間は3年や5年といったスパンで、期間終了時には再度公募・選定が行われるのが一般的です。
このように、学童保育所の指定管理者は、各自治体が「よりよいこどもたちの居場所をつくってくるか否か」という視点で比較・検討し、最もふさわしいと判断された法人・団体が担う仕組みになっているのです。
3. 指定管理者制度のメリットとは?
指定管理者制度によって、自治体や利用者はどのような恩恵を受けられるのでしょうか。今回は3つのメリットを取り上げてみました。
《メリット① 》多様なノウハウを活用できること!
様々なノウハウを持つ民間の団体や法人が運営することで、それぞれの特色ある取り組みが学童保育所の運営に持ち込まれます。例えば、英語レッスンや工作・科学実験などのワークショップを定期的に開催する学童保育所や、地元の農家と協力して収穫体験をする学童保育所など、自治体の直営(公設学童)ではなかなか手が回らないような独自のプログラムが展開されることもあります。
こうした取り組みはこどもたちの好奇心を刺激し、「ただ預かる場所」から「新しい体験ができる楽しい居場所」へと学童保育所を進化させてくれます。
《メリット② 》効率的な運営ができること!
民間の法人や団体は限られた予算の中で工夫する力に長けています。例えば、地域の大学生をアルバイトとして活用し、こどもたちの見守りと学習支援を同時に実現するなど、コストを抑えつつこどもたちと保護者の利益につながる仕組みを作りやすいのです。
また、大手の法人の場合は複数施設を運営していることが多く、職員の欠勤や退職などの際にも施設間の連携によってすぐに人員の補填ができ、余裕のある職員配置を実現しやすいというメリットもあります。
自治体にとっても、直営で人件費や大量の事務を抱えるより、指定管理によって効率的に運営してもらうことができるのは大きな魅力といえるでしょう。
《メリット③》 地域との連携が深まりやすい
地域密着型のNPOや社会福祉法人が指定管理として運営をする場合、地元ボランティアを巻き込んだイベントや、地域企業と連携した活動が行われることもあります。こうしたつながりはこどもたちにとって「地域に見守られている」という安心感につながります。

4. 指定管理者制度の課題は?
学童保育所の指定管理者制度には多くのメリットがある一方で、見逃すことができない課題もあります。
【課題① 】契約期間の制約があること。
指定管理は数年ごとに契約が切り替わります。継続して委託されれば問題ありませんが、運営する法人・団体が変われば学童保育所としての運営方針や指導員の顔ぶれが大きく変わってしまうということも少なくありません。こどもたちにとっては「慣れた先生が急にいなくなる」という体験となり、不安や寂しさにつながることもあります。保護者も「この先生(この運営団体)だから、安心して預けていたのに…」というように落胆したり不信感を抱いたりしてしまう可能性があります。
【課題② 】運営の質にばらつきが出る可能性がある。
法人の経験や財政基盤、提供するサービスに差があるため、学童ごとに運営の質が大きく異なってしまう場合があります。「安心安全で充実したサポートを受けられる学童」と「最低限の人員・プログラムしか用意されていない学童」との差は、地域間格差にも直結します。同じ地域内で複数の指定管理者が運営する学童がある場合は、注意が必要です。
【課題③】 人材の育成や確保が難しくなること。
学童指導員の仕事は責任が重く、こどもたちと長時間向き合う必要があるという負担に対し、待遇は必ずしも十分であるとはいえません。特に指定管理の法人・団体は自治体からの委託料という限られた予算でやりくりするため、給与や労働条件が改善されにくく、人材の流動化が起こりがちです。その結果、こどもにとって安心できる「長く関わる大人」が不足してしまうという可能性があります。
上述したように大手法人であれば他施設で勤務するスタッフを異動させることで欠員補充はできるかもしれませんが、コロコロと職員が変わる環境は決して健全なものとはいえません。
人材の採用や育成は自治体で担当・管理できなくとも、労働環境や職員研修に実施実績などについては定期的に調査をし、確認をしておくことが必要不可欠となります。
まとめ
学童の指定管理者制度は、単なる運営方法の一つではなく、こどもたちや保護者の日常生活に大きく関わる仕組み。民間の力を取り入れることで新しい取り組みや柔軟な運営が可能になる一方、安定性などの面では大きな課題も抱えています。
保護者としては、こどもを預ける際に「この学童は一体誰が運営しているのか」や「どういう理念を持った法人なのか」に少し目を向けてみると安心につながります。また自治体や運営法人にとっても、利用者の声をしっかり受け止めながら改善を続けることが求められます。
制度そのものがゴールではなく、「こどもたちが放課後を安心して、そして楽しく過ごせる居場所をつくること」が一番大切であり、指定管理者制度はそのための仕組みにすぎません。制度のメリットを生かしながら、課題を一つずつ乗り越えていくことで、学童保育所はより充実した安心できる場所へと育っていくでしょう。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。