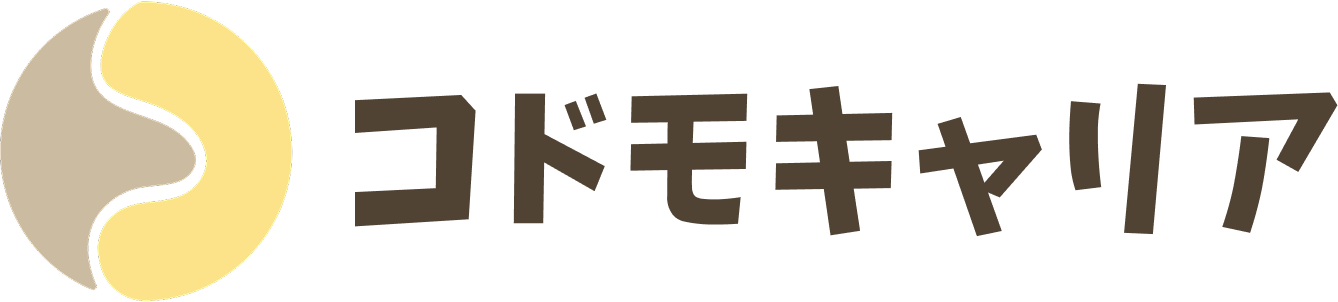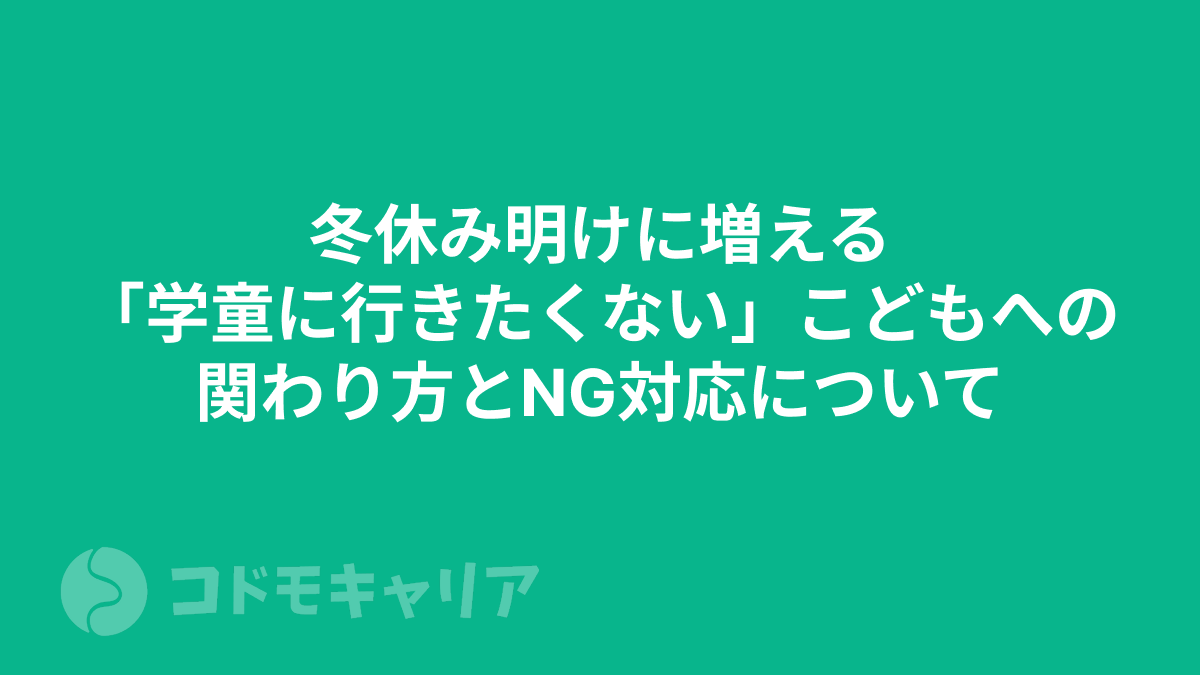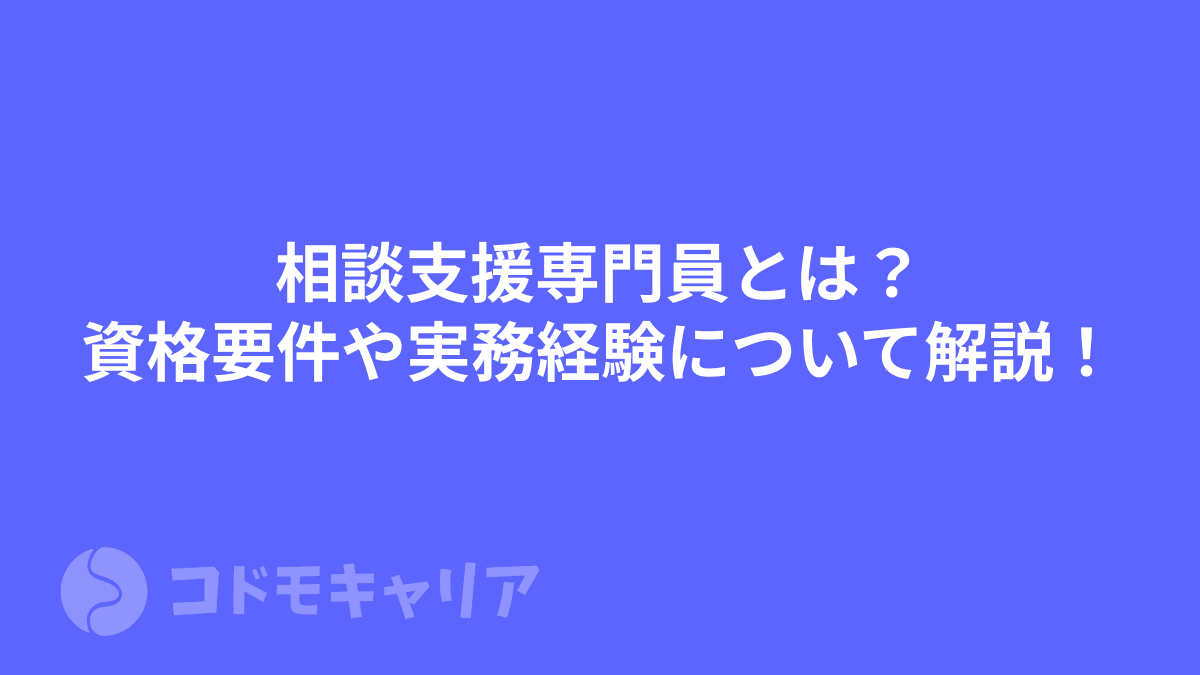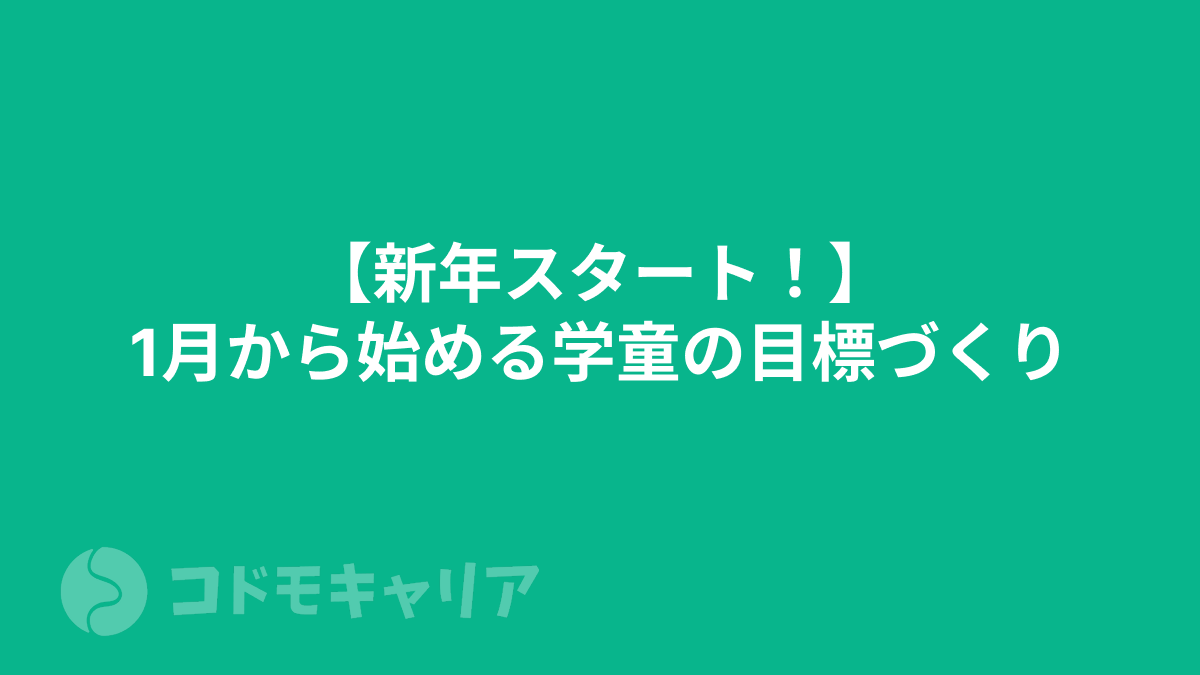タグで絞り込む
キーワードから探す
【遊びで育つ非認知能力】協調性・自己表現力が伸びる秋のプログラム4選
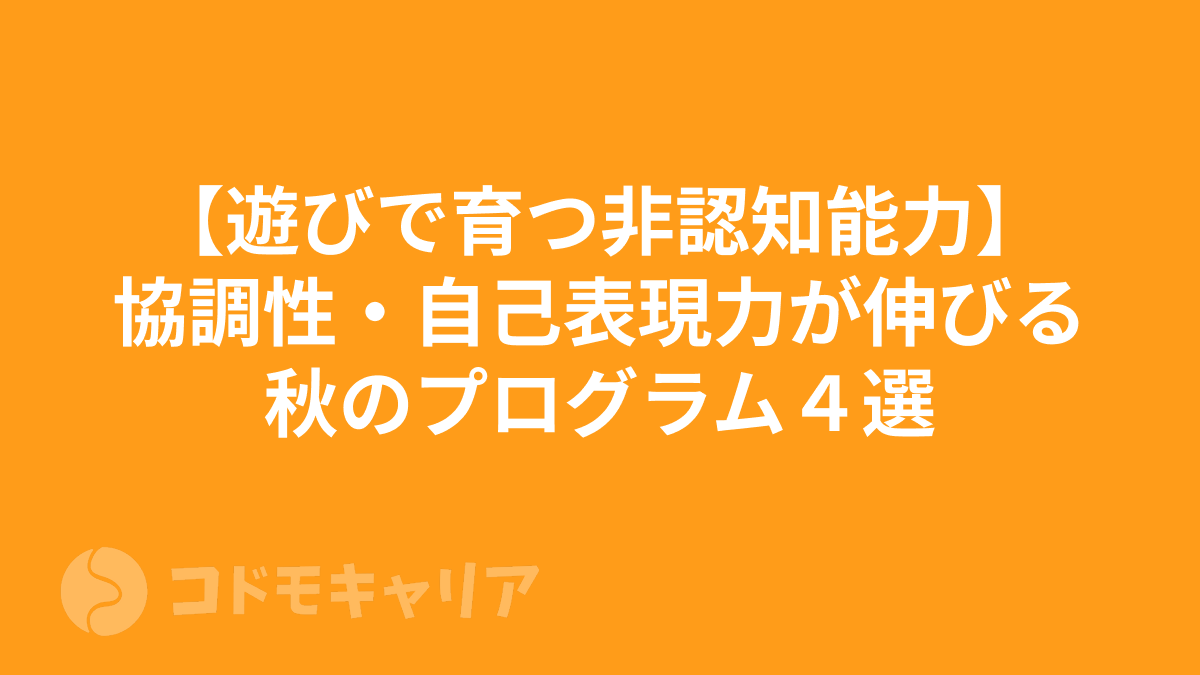
学童
実践事例
あそび
非認知能力
学童保育所では、毎日たくさんのこどもたちが全力で遊び、実体験の中から多くのことを学んでいます。そして、気候が穏やかで、外遊びや創作活動にぴったりな秋の季節は、「非認知能力」の向上を意識したプログラムを取り入れるチャンスです。
今回は、秋らしさを感じながら楽しめる遊びや工作を通して、こどもたちの協調性や自己表現力が自然に伸びるようなプログラムを4つご紹介します。
◎非認知能力とは?
「非認知能力」という言葉は、近年教育界で大きな注目を集めています。「認知能力」は読み書き計算などの「数値で測ることができる能力」であるのに対して、「非認知能力」は人として生きる力の土台をつくる「点数化することのできない能力」のことを指します。
たとえば、
• 仲間の意見を聞き、ともに生きていくための「協調性」
• 自分の気持ちを他者へ伝える「自己表現力」
• 困難に直面してもあきらめない「粘り強さ」
• 失敗しても立ち直る「回復力(=レジリエンス)」
これらの力は、決して一朝一夕で身につくものではありませんが、遊びの中にはその“練習の場”がたくさんあります。大人が教えようとしなくても、こどもたちは自分たちで試行錯誤を繰り返し、相手との関わり方や自分の感情との付き合い方を学んでいくのです。
学童保育所は、学校でも家庭でもない第三の居場所。勉強やスポーツなどの力を伸ばしたり評価したりする必要がない場所だからこそ、「目に見えない大切な力=非認知能力」が育つ場として、非常に効果的であると考えられています。
◎非認知能力が育つ秋のプログラム例
秋ならではの良さを味わいながら、こどもたちの協調性や事故表現力が伸びるようなプログラム例を今回は4つご紹介します。ぜひ、こどもたちの様子や各学童現場の状況に応じて活用してみてくださいね。
①落ち葉アートで創造力と協調性を育もう!
秋といえば、落ち葉。公園やお散歩で通る道などに落ちているたくさんの綺麗な葉を拾って、並べて、貼って…。そんな定番の落ち葉遊びは、そのままでも十分面白く、創造力が刺激される楽しい活動ですが、素材の準備から作品作りまでグループで取り組んでみることで「協調性」も一緒に育っていきます。
例えば、いくつかのグループに分かれたこどもたちに「今からここに落ちているものを使って、秋の風景を作ってみよう!拾う時間は30分です」などと声をかけ、落ち葉・木の実・枝などを集めるところからスタート。
「こんな葉っぱが落ちてたよ!」や「どんぐり見つけた!使えるかな?」などと、こどもたち同士が相談しながら遊びを続けるうちに、グループ内で自然とコミュニケーションが生まれます。拾ったものを施設に持ち帰ってからも、あえて一人一作品ではなく、グループごとに落ち葉アートを制作してみることで、会話を楽しみ、作業を分担しながら工作を楽しむことができます。
この時、大人が指示指令を出したり見本を示したりせずに、できるだけこどもたちの話し合い・流れのままに任せてみることがポイント。仮にグループ内で衝突が起きたときも、「どうしたら全員の意見を取り入れられるかな?」とこどもたちに投げかけることで、話し合う力や折り合いをつける経験が積み重なっていきます。
完成した作品は、学童の壁に飾ったり、写真に撮って掲示したりすると、チームの達成感がより高まります(コンテストのような順位付けは必ずしも必要ありませ)。「自分たちで協力して作りあげた」という自信は、自己効力感にもつながります。
②協力型の外遊びでチームワークを育もう!
涼しくなった秋は、外での活動に最適な季節です。鬼ごっこなどの定番遊びも、少し工夫することで協調性を高める遊びに変わります。
たとえば、「協力リレー」として、2人1組で風船を落とさないように運んでみたり、「ペア鬼」として手をつないで逃げるなど、相手の動きを意識しながら動くような仕掛けを取り入れてみると良いでしょう。
勝ち負けよりも「どうすればうまく協力できるか」を考える過程が大切で、うまくいかないときには仲間と相談して改善を試みる…という繰り返しが、相手を思いやる力や話し合いを楽しむ感覚を自然と育ててくれます。また、遊び終わった後に「どんな工夫をした?」や「難しかったところは?」とふり返る時間を作ることで、遊びの体験がより深まります。
③ハロウィン工作で自由な発想を楽しもう!
10月といえばやっぱりハロウィン! 仮装や飾り付けは、創造力や自己表現力を育てる絶好のチャンスです。ただ大人が考えた見本通りの工作をするだけではなく、「自分らしさ」を大切にできるようなテーマ設定を意識しましょう。
たとえば、「”自分がなってみたいオバケ”をテーマにした仮装マスクづくり」として、自分がなりたいオバケや空想上の生き物をモチーフに仮装マスクを作ってみたり、「紙コップと毛糸で作る“オリジナルゆらゆらオバケ”づくり」として、好きな色の毛糸を選び好きな顔を描いたオリジナルオバケの玩具作りをしたりしてみるアイディアがあります。
「怖いオバケじゃなくて、かわいいオバケにしようかな」や「ツノが生えていたら面白いかも!」といった会話をしながら、こどもたちは自分の考えやイメージを言葉にし、どんどん形にしていきます。
大人は「うまく作れているか」よりも、「どんな気持ちで作ったの?」と作品の背景に目を向けるのがポイントです。季節のイベントを楽しみながら、ぐんぐんと非認知能力が育まれること間違いなしです。
④秋の冒険クエストにチャレンジしよう!
色づいた葉っぱやどんぐりに虫の声…秋の季節に外へ出れば、自然の中にたくさんの発見と学びが隠れています。この季節の良さを生かして、「秋の冒険クエスト」といったイベントを企画するのもオススメです。みんなで力を合わせながら様々なミッションをクリアしていくことで、探究力や好奇心、思考力や協調性など幅広い非認知能力の向上が期待できます。
例えば「まん丸などんぐりを5つ見つけよう!」や「秋の音を10個探そう!」などのミッションを大人からこどもたちに伝え、チームで協力しながら取り組んでもらいましょう。実際に手と足を動かしながら、仲間とともに体で学んでいく時間は、大きな成長の機会になります。
◎非認知能力を育む関わり方のコツ
上記で紹介したような遊びのプログラムそのものも大事ですが、大人の関わり方によってこどもの学びや成長度合いは大きく変化します。以下の3つのポイントを意識することで、こどもたちの活動をより深い学びに繋げていきましょう。
① 「評価」ではなく「共感」しよう!
「上手にできたね!」といった結果の評価よりも、「工夫したね!」や「楽しそうにやっていたね!」などと過程を積極的に言葉にして伝えましょう。努力や工夫を認めてもらえることで、こどもたちの自己肯定感は高まります。
② 「失敗」も肯定しよう!
新しい遊びや体験には失敗はつきものです。でもうまくいかなかった時こそ、成長のタイミング。単なる失敗で終わらせるのではなく、成功の道への第一歩であると感じてもらえるような声かけを意識しましょう。できていたところや良かったところを見つけて伝えてあげたり、次回に活かせるようなアドバイスをしたりすることで、新たな挑戦や遊びに対する前向きな姿勢が育ちます。
③大人も一緒に楽しもう!
そもそも非認知能力とは、大人が一生懸命に「伸ばそう」とするものではなく、こどもの意思によって「伸びる」もの。大人が笑顔で遊び、一緒に楽しんでいるという安心感があることで、こどもたちはありのままの自分を表現しやすくなり、より多くのことを学んでいきます。「やらせる」ではなく「一緒にやる」という姿勢が非常に大切なのです。
まとめ
秋は、自然の変化や季節のイベントを活かしやすい絶好の時期。こどもたちの心と体ものびのびと遊びに向かう季節です。落ち葉を拾って仲間と協力して作品をつくったり、ハロウィン工作で自分らしさを表現したり、外で思い切り体と頭を動かして遊んだり…そのようなひとつひとつの体験の中に、「非認知能力を育てる大切な学び」が隠れています。
ぜひ、日々の活動に「非認知能力を育てる視点」を少しだけ意識してみてください。これまでは単なる遊びと思っていた時間が、「こどもたちの未来を彩る豊かな学びの場」へと変わっていくはずです。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。