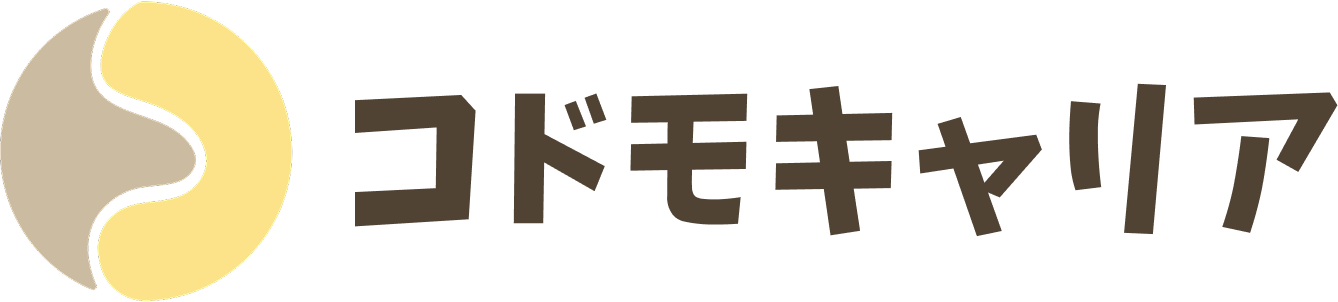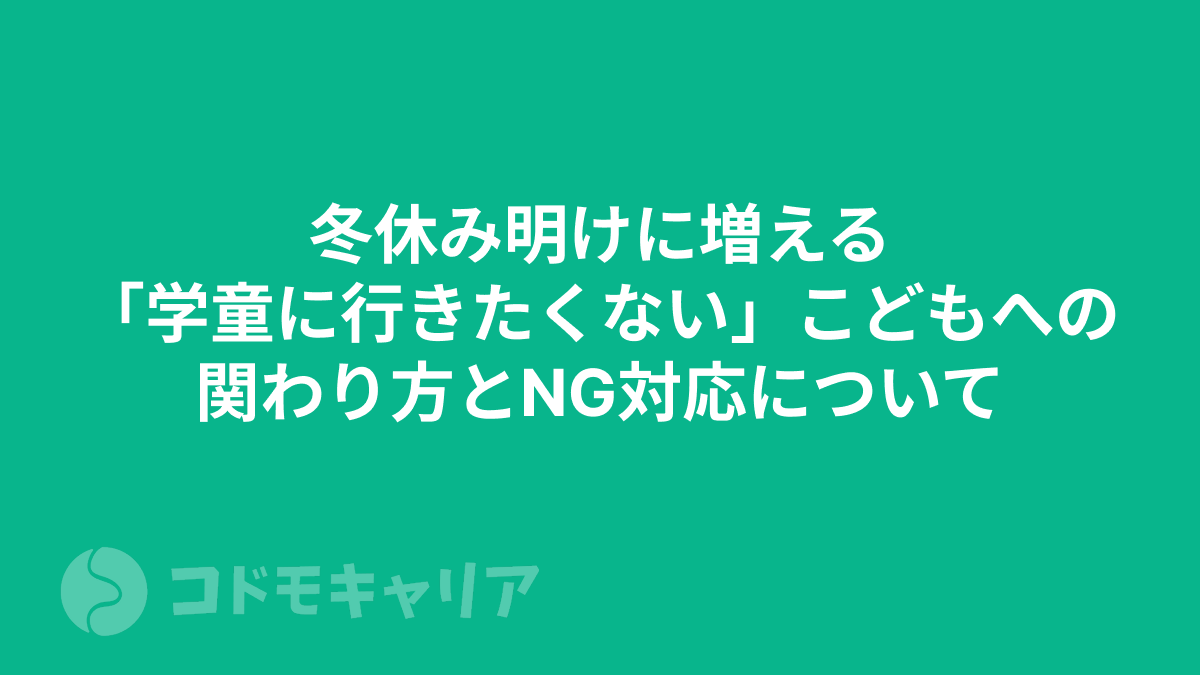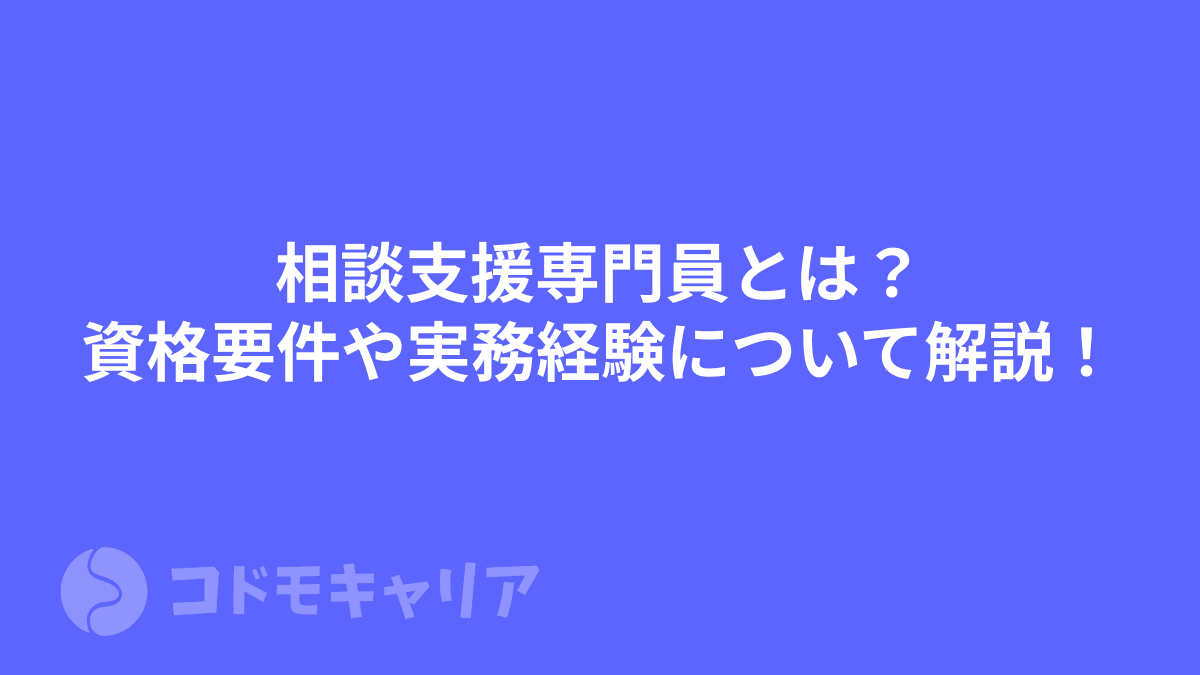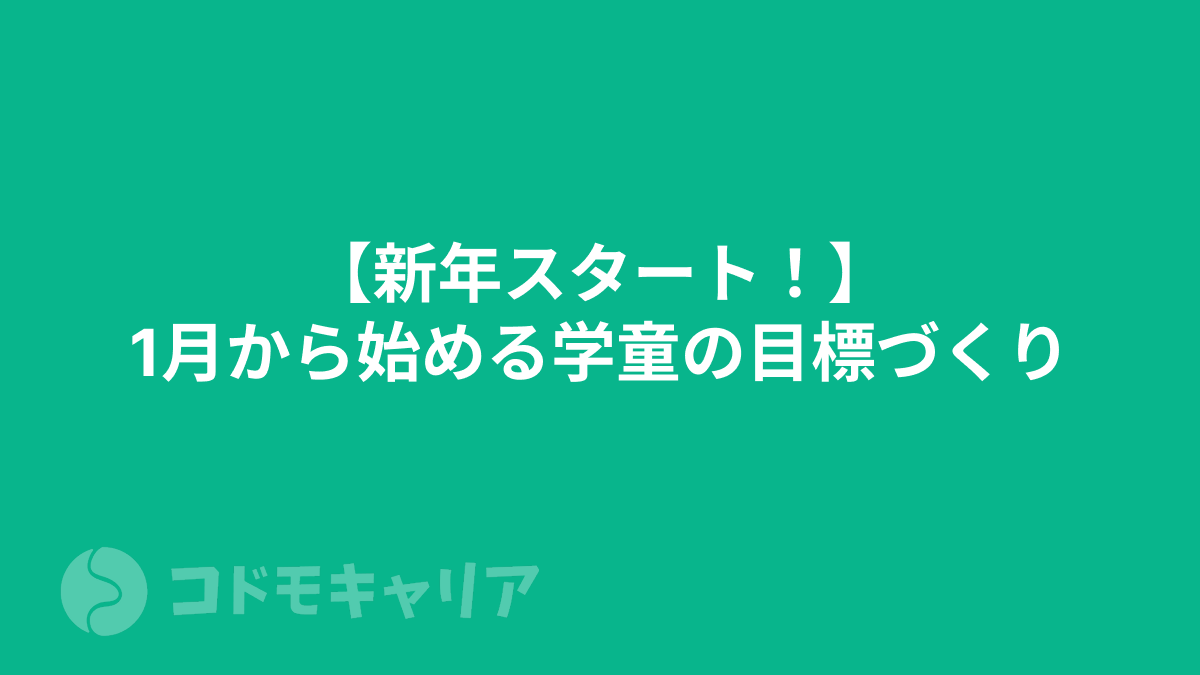タグで絞り込む
キーワードから探す
【横浜・川崎市】学童にはどんな補助金が出ている?自治体の特徴を徹底解説!
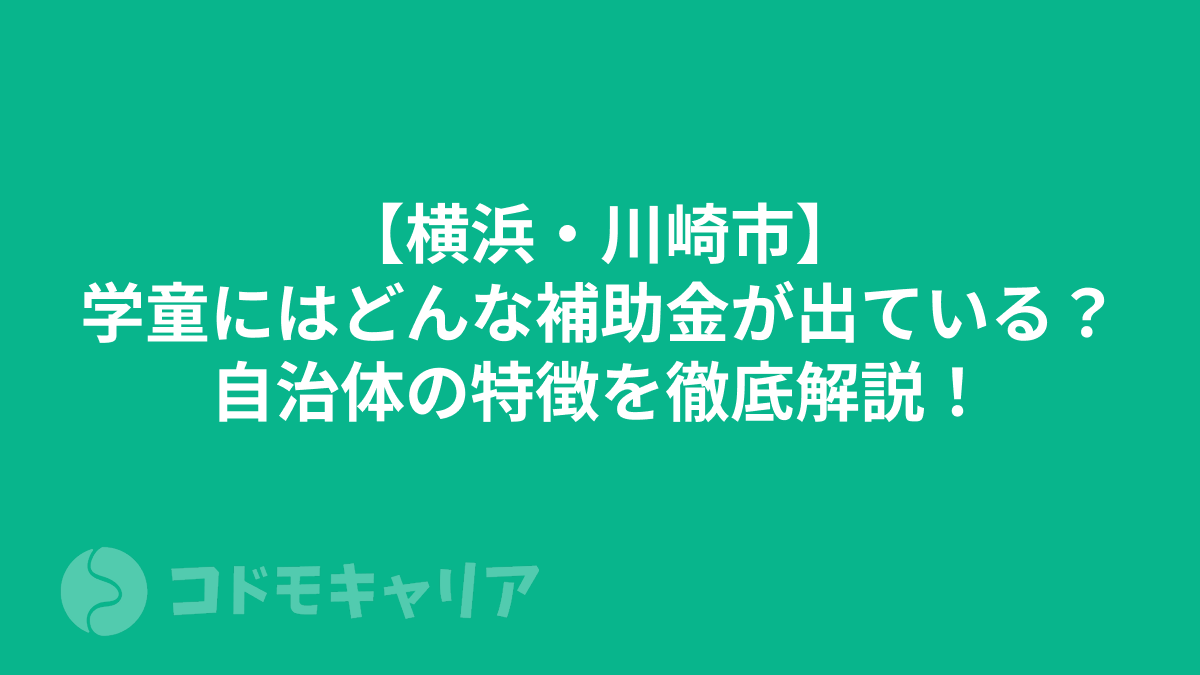
学童
実践事例
公立学童
民間学童
学童経営
首都圏の中でも共働き世帯が多く、人口密度も高い神奈川県の「横浜市」と「川崎市」。どちらの都市でも、こどもたちの放課後の居場所である学童保育所の需要は年々高まっています。
そして、両市ともに待機児童の解消や学童支援員の確保は依然として大きな課題となっており、「公設民営学童」や「民設民営学童」といったそれぞれの運営モデルを組み合わせながら、多様な学童の在り方を模索しています。
その中で、様々な学童保育所を継続的に運営していくために特に重要なのが自治体による「補助金」制度です。
本コラムでは、横浜市と川崎市の学童保育に対する補助金制度を比較しながら詳しく解説していきます。

1. 横浜市の学童保育制度と補助金の仕組み
横浜市では、児童福祉法に基づく「放課後児童健全育成事業」として、公設公営クラブ・公設民営クラブ・民設民営クラブの3つの運営形態があります。そのなかでも、横浜市で主流となっているのは公設民営クラブです。
公設民営クラブとは、市が整備した学童保育所の施設を法人に委託し、運営を行う仕組みのことをいいます。公設民営クラブには運営委託料として人件費・事務費などが支給されており、一定の安定収入を得ながら地域に根ざした学童保育所の運営を行うことが可能です。
なお、運営委託料の内訳には以下のようなものが含まれます。
・放課後児童支援員や補助員の人件費
・備品・教材費
・管理運営費
・安全対策費
委託先は、運営実績や地域連携体制などが審査基準となって自治体の公募により選定され、市の指針に沿った運営体制を整えることが求められます。
横浜市は公設民営型のクラブへの委託が多い一方で、民間事業者が独自に運営する「民設民営型」の学童にも「横浜市放課後児童クラブ事業費補助金」という補助金を交付しています。
運営費補助では、支援員人件費・家賃・教材費などが対象となり、児童数や開所時間に応じて単価が設定されます。1クラブあたり年間数百万円規模の補助が受けられるケースも多く、一定の運営安定につながっています。
また「放課後児童支援員等キャリアアップ処遇改善費補助」として、支援員の処遇を改善するための補助金も用意されていたり、施設整備費補助として、新規開設や改修にかかる費用の1/2〜2/3を上限として補助が行われたりもしています。ただし対象となるのは設備・工事費などで、年度ごとの申請と実績報告が必要になるので注意が必要です。加えて、補助の対象となるクラブは、市が定める開所時間・支援員資格・安全管理基準などを満たしていることが前提条件となりますので、活用を検討する際はよく申請要件を確認してみてください。
横浜市の補助金制度についてまとめると、「公設民営学童クラブ」を広く運営することで委託費として補助をしつつ、「民設民営学童クラブ」にも運営費や施設整備費として補助を行う仕組みが出来上がりつつあるといえます。
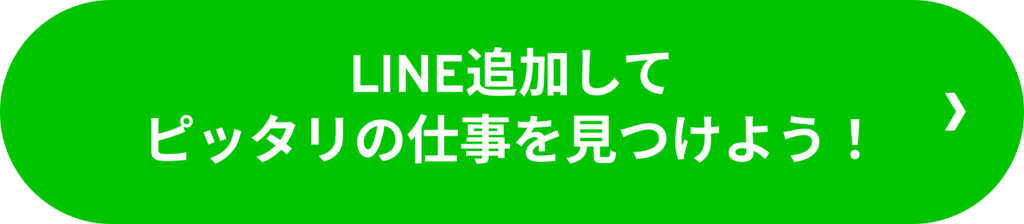
【2】川崎市の学童保育制度と補助金の仕組み
一方川崎市では、全国的にも珍しい「二層構造」の放課後支援体制を採用しています。
具体的には、すべての小学校区で実施される全児童対象の「わくわくプラザ事業」と、保護者が就労等で家庭で保育できない児童を対象とする「放課後児童クラブ(学童保育)」が併存した「二層構造」となっています。
「わくわくプラザ事業」とは、小学校の余裕教室などを活用して、放課後や土曜日、夏休みなどの長期休業期間中に、子どもたちの安全・安心な居場所を提供し、多様な体験活動や学習機会を提供する川崎市独自の事業です。利用料は原則無料で、就労家庭ではなくても利用できる居場所です。
一方、いわゆる学童事業を担っているのは後者の「放課後児童クラブ(学童保育)」であり、主に地域団体や民間事業者、保護者によって民設民営されています。それらに対し、市は「川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業」として補助を交付するなどの支援を行っていますが、川崎市の学童に対する補助金制度はまだまだ不足しているという現場の声もちらほらと耳にします。
運営団体や保護者が自主的に運営している放課後児童クラブ全てに補助がおりているわけではないため、どうしても負担が大きく、安定した継続運営が難しくなってきている施設も多く存在しています。限られた予算内では学童支援員の処遇改善にもなかなか踏み込めないため、長期間勤続できるスタッフの少なさも課題といえるでしょう。
3. 横浜市と川崎市の補助金制度を比較すると…?
横浜市と川崎市は、いずれも民間学童に対して運営費・整備費の補助制度を整備していますが、その運営モデルには明確な違いがあります。
横浜市は「公設民営型」が主流であり、市が整備した施設を法人に委託して運営を行う仕組みが多く見られます。市の基準や運営方針に沿う必要がありますが、その分委託料による安定した運営が可能であり、地域全体で均質なサービスを提供しやすいという強みがあります。
一方、川崎市は「わくわくプラザ事業」を除くと「民設民営型」が主流であり、各運営者が自ら施設を構え、独自の方針でクラブ運営を行う自由度が高い点が特徴です。市は運営費・整備費・加算補助などを通じて支援していますが、各クラブの創意工夫や地域性が色濃く反映される構造となっています(=各運営主体の負担が大きい構造ともいえます)。
つまり、横浜市が「行政主導で安定した運営モデル」を形成しているのに対し、川崎市は「民間主体で多様性のある運営モデル」を展開しているということです。
両市ともに年度申請制で、運営報告や現地確認などの審査が必須である点は共通していますが、補助金の算定方式や支援範囲には違いがあり、運営者は自らの事業計画に応じて最適な補助制度を活用することが求められます。
4. 今後の課題と展望
横浜市は、児童数の増加に対応するために「公設民営クラブのさらなる拡大」と「民設民営クラブの支援強化」を両立させる方針を掲げています。特に、学童支援員の人材確保や長時間開所への支援、民間との協働による質の高い運営体制づくりが今後の重点課題とされています。
また、川崎市は「わくわくプラザ」と「放課後児童クラブ」を組み合わせることで、すべての児童を包摂する放課後支援を目指しています。特に近年は、障害児受け入れ体制の強化や支援員研修の充実、ICTの活用など、質の向上に重点を置いているようです。加えて、上述のとおり「放課後児童クラブ」に対する支援の充実化も、強く求められている課題といえるでしょう。
共働き家庭の増加とともに、学童保育のニーズは「量の確保」から「質の向上」へとシフトしているため、横浜市・川崎市のいずれも、民間事業者が持つ教育的ノウハウや柔軟な発想を活かした新しい放課後支援のかたちを模索していく必要がありますね。
まとめ
横浜市は「公設民営モデルによる安定運営」を、川崎市は「民設民営モデルによる自由運営」をそれぞれ特徴としていましたが、どちらの市も補助金制度を通じて民間の参入を支援し、放課後の多様なニーズに応える体制を整えていく過程にあるといえます。
これからの学童保育所には、単なる預かりではなく、「遊び・学び・居場所」を一体的に支える新しい価値づくりが求められています。自治体による充実した補助金制度(行政支援)と民間独自の魅力や柔軟性が合わさっていけば、こどもたちの放課後はより豊かで、多様な可能性に満ちた時間へと進化していくことでしょう。

career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。