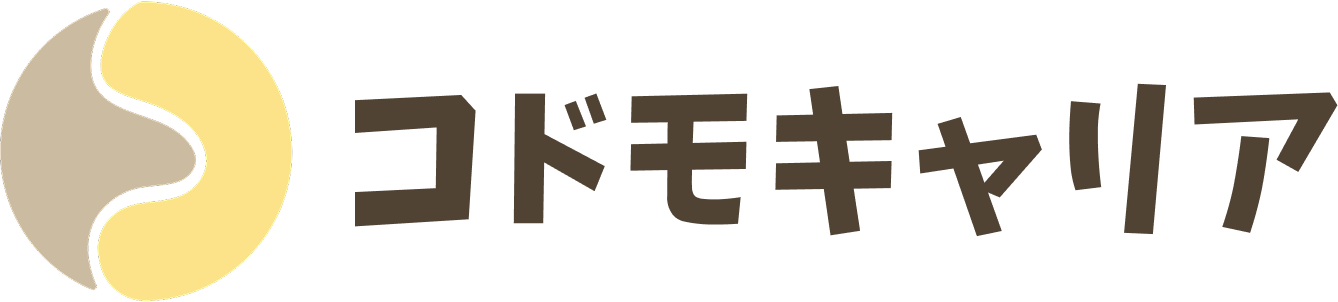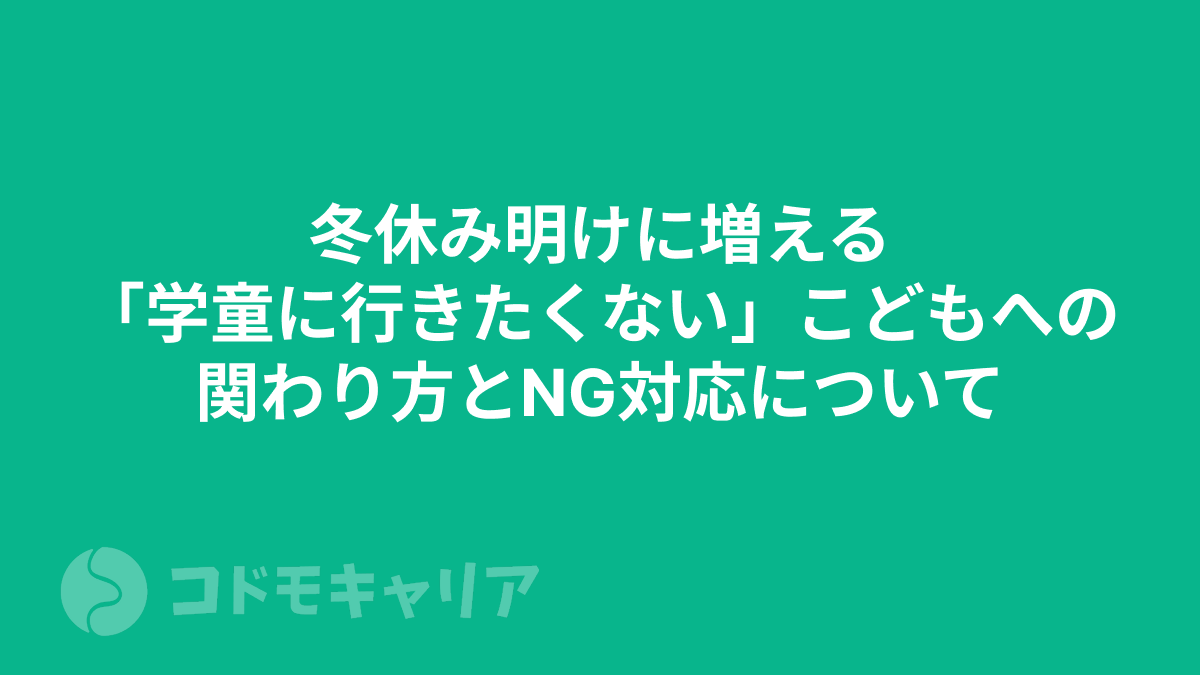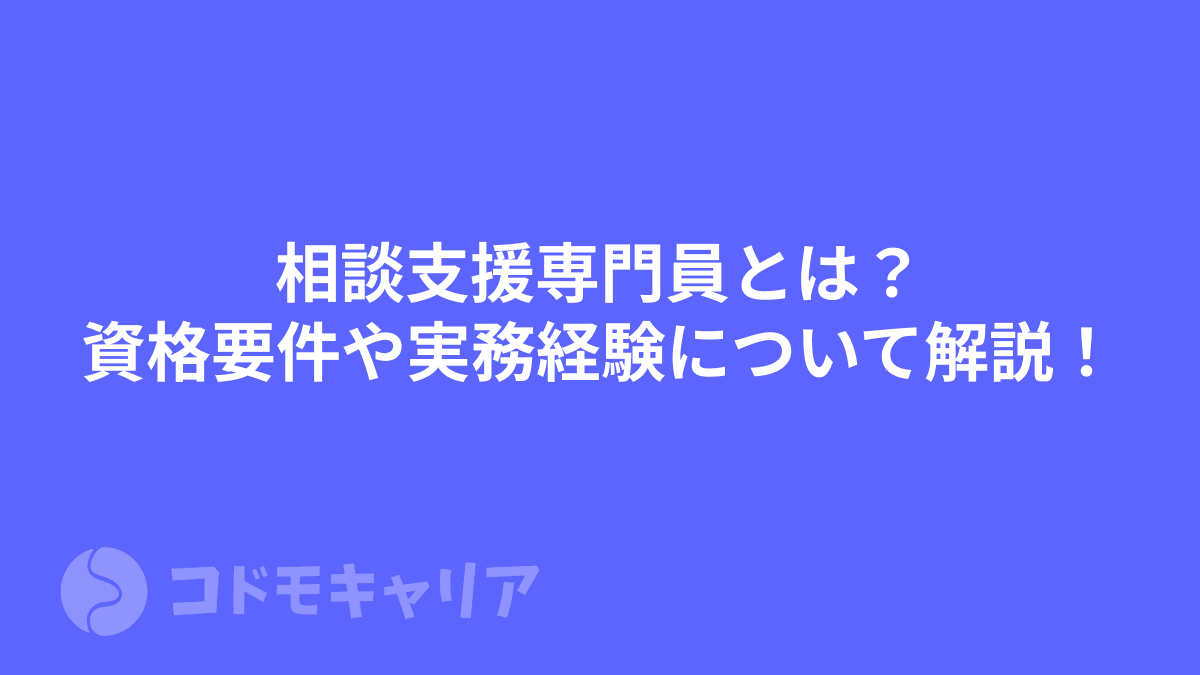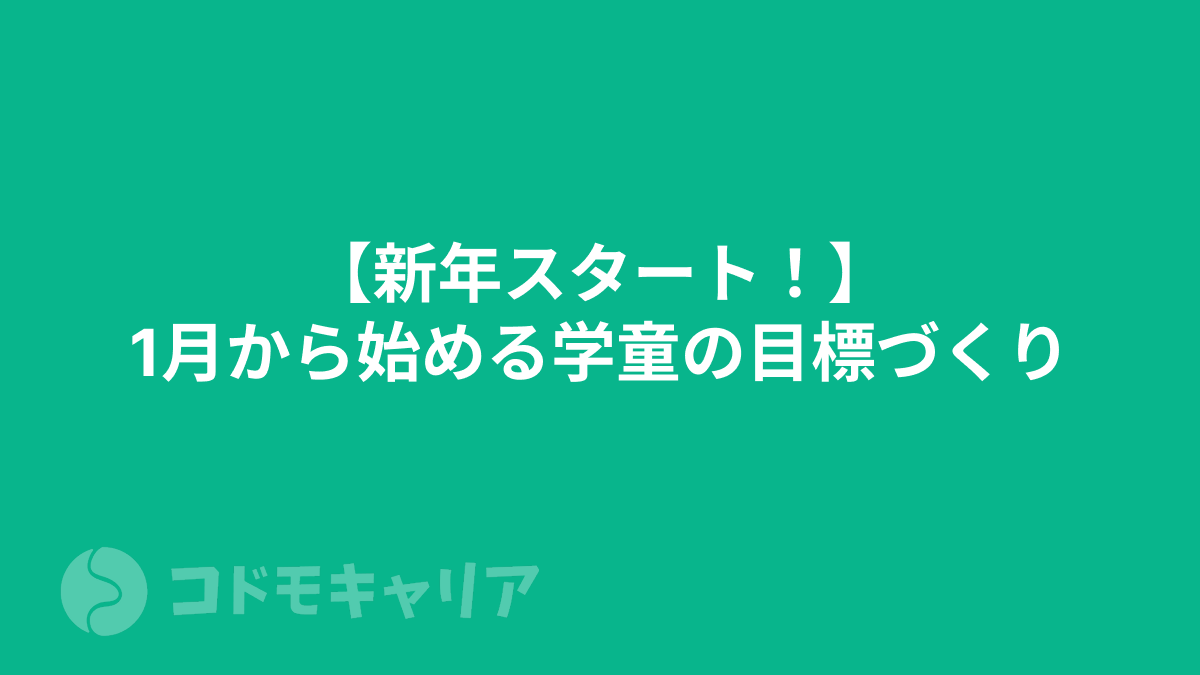タグで絞り込む
キーワードから探す
【グレーゾーンのこども】学童で出来る支援と、家庭や学校との連携ポイント
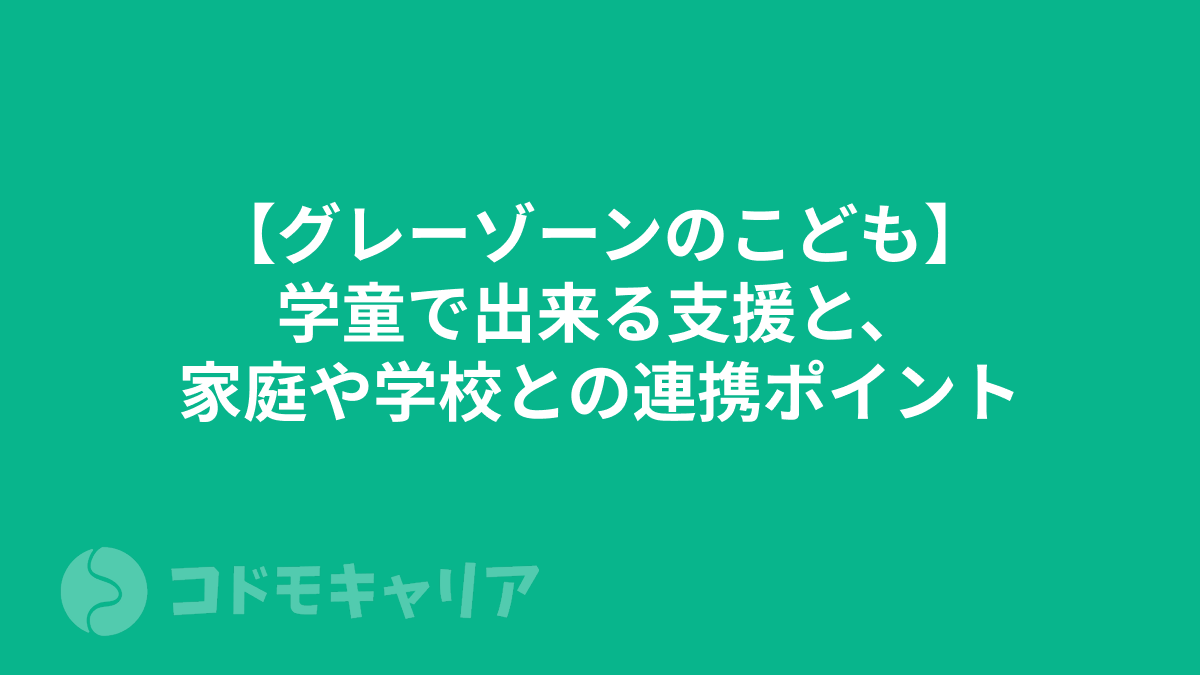
学童保育所に通うこどもたちの中には、「発達障がい」と診断されているわけではないけれど、集団行動やコミュニケーションが苦手だったり、感情の起伏が激しかったりする子がいます。こうしたこどもたちはいわゆる「グレーゾーン」と呼ばれ、支援が届きにくい立場にあるといわれています。
学校では「なんとなく扱いづらくて困っている子」、家庭では「なんだか育てにくい子」と見られることもありますが、実際のところはこども自身が最も生きづらさを感じていることが少なくありません。学童保育所は、そのようなこどもたちが安心して過ごせる「第三の居場所」として大きな役割を担っています。
では、学童保育所の現場では具体的にどのような支援ができるのでしょうか。そして、学校や家庭とはどのように連携していくことができるのでしょうか。
1.グレーゾーンとは?
「グレーゾーン」とは、発達検査で数値的には診断基準を満たさないものの、日常生活の中で「過ごしづらさを感じるような特性」が見られるこどもたちを指します。たとえばグレーゾーンのこども達には、このような特徴が見られます。
・集団行動が苦手
・長時間じっと座っていられない
・空気を読まない行動をしてしまう
・注意されると強く反発する
・切り替えが苦手で感情が爆発しやすい
・音や光などの刺激に敏感である
このような特性を持つグレーゾーンのこどもたちは、発達障がいのという診断がくだされている子に比べて周囲からの理解が得られにくく、時に「わがまま」や「反抗的」と誤解されがちです。
また、グレーゾーンのこどもたちは診断がないことで、学校の特別支援学級に入ることが出来なかったり、学童保育所の加配対象にならなかったりというケースも多く存在します。保護者自身がこどもの特性を受け入れられず、「うちの子は発達障がいではないから」という考えのもと、放課後デイサービスや療育機関などのサポートを受ける機会を逃してしまうこともあります。
そのためグレーゾーンのこどもたちにとっては、学童保育所が 「適切な個別支援の場」 となることが非常に重要となってきます。ほっと一息つける学校と家以外の場所である学童保育所で、一人ひとりのこどもの特性や行動の背景を丁寧に見とっていくことが、支援の糸口になります。

2.学童における支援の基本姿勢
学童における支援において最も大切なことは、「出来ないこと」ではなく「出来ること」に注目する姿勢です。
どうしてもグレーゾーンのこどもたちは「どうしてこんなこともできないの?」や「みんなはできているのに」と注意をされたり出来ないというレッテルを貼られたりしがちです。しかし、一括りに「この子は出来ないばかり」と評価するのではなく、「この子が出来ることは何だろう?」と視点を変えて見守ることが重要です。
例えば、一見片付けが苦手な子でもよく観察してみると「好きな色の箱には入れられる」や「同じ形を集めるのは好きそうである」ということがあります。また「1分だけなら集中して片付けられる」という子もいるでしょう。そのような「出来る」に着目すると、「赤色のものを片付けるチャレンジ」や「1分片付けチャレンジ」などと称し、片付ける範囲や時間を区切ってみたりすることができます。「出来る」を見つけて伸ばせるような日々の小さな工夫の積み重ねが、こどもたちの自己肯定感を育てていきます。
また、言葉の伝え方にも工夫が必要で、「静かにして!」と注意するよりも「声が大きくてびっくりしちゃった。このくらいの声で話せる…?( 実際に適正な声の大きさでスタッフが喋る )」と具体的に伝えると分かりやすいです。また「すぐに動いて」や「しっかり片付けて」などの曖昧な指示では混乱する子も多いため、「何を・いつ・どうすればいいか」を明確にすることも大切です。
そして、問題行動をとったこどもに声をかける前には「なぜそうしたのか」を考える姿勢を忘れないようにしましょう。問題行動と呼ばれるような感情的な反応の裏には、疲れ・不安・悲しみ・感覚の過敏さなど、何かしらの理由が隠れています。ただ叱りつけるのではなく、その背景を理解しようとする姿勢自体が、こどもにとって大きな安心感につながるはずです。
3.環境づくりの工夫
前述のような心構えや意識を持つことに加え、学童施設の環境を物理的に整えることも、グレーゾーンのこどもにとっては大きな支援になります。ポイントは「刺激を減らし、予測しやすい環境にする」ことです。
たとえば、自由時間とおやつの時間、宿題の時間など、1日の流れをホワイトボードにイラスト付きで掲示すると、こどもが先の見通しを持ちやすくなり、不安や混乱が減ってトラブルを未然に防ぐことができます。
また、音や人の動きに敏感な子どもには、「静かなコーナー」や「ひとりになれるスペース」を用意するのも有効です。決して隔離ではなく、周囲の音や視線から身を守る「安心できる選択肢」として存在させることが重要です。
さらに帰りの会や集会などの場面で、スタッフの話を聞いてほしい時には、見える場所に玩具やポスターなど気が散ってしまうようなものを極力隠して、刺激を減らすことも効果的です。
「怒らなければならない(こどもが困ってしまう)環境・状態をそもそも作らない」というのが理想的です。
4.家庭や学校との連携について
学童での支援をより効果的にするには、家庭や学校との連携が欠かせません。
しかし、学童での様子を保護者の方に情報共有をしようと思っても、保護者の中には「お子さんには特性があり…」と伝えられることに抵抗を感じる方も少なくありません。そのため、伝え方には細やかな配慮が求められます。
例えば、いきなり「お子さんには気になる行動があります」と伝えるよりも、「最近○○のときにすごく集中していましたよ」とポジティブな話題から始めることで、保護者は安心して耳を傾けてくれます。そのうえで、「少し気になる場面もあるので、一緒に工夫していけたら…」と、協力関係を築く形で伝えると良いでしょう。
また、学童での様子を日々の連絡帳や送迎時の会話で共有することも大切です。家庭での困りごとを聞く機会にもなり、自然と信頼関係が深まっていきます。何か困ってから初めて連絡をするのではなく、普段からコミュニケーションをとっておくことで連携がしやすくなるのです。
家庭との連携に加えて、グレーゾーンのこどもは場所によって見せる姿が異なることがあるため、学校との連携も非常に重要です。学校で我慢して良い子で過ごしている分、学童で爆発し手がつけられない…というケースもあれば、学童では穏やかに過ごしていても、学校では注意を受けてばかりで困っている…という逆のケースもあります。
「家庭ではこのように過ごしている」「学校ではこのような姿が見られる」といった多角的な視点を集めることで、その子の行動をより正確に理解でき、学童だからこそ出来る支援の形を探りやすくなります。
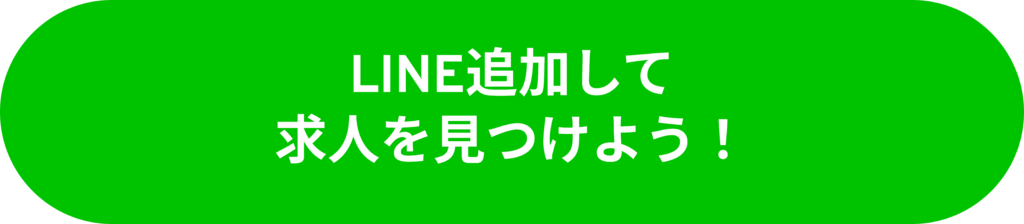
5.支援員が抱えやすい葛藤って?
「グレーゾーンの子自身が一番困っているのだ」と頭では理解が出来ても、実際にその子の対応をし続けることはスタッフにとっても負担が大きいものです。「何度言っても同じことを繰り返す」や「他の子への影響が気になる」、「保護者と今後の方針や意見が合わない」…そんな場面で疲弊してしまうこともあるでしょう。
大切なのは、一人のスタッフがその悩みや苦しさを抱え込まないことです。施設全体で定期的にミーティングを設け、困りごとを共有しあったり、外部の専門家や発達支援センターに相談をしたりといった仕組みを整えることで、スタッフ自身の安心感も守ることができます。
また、スタッフや学童の施設内で「完璧な対応」を目指しすぎないということも大切です。支援は決して一人の力・一つの施設内で完結するものではありません。時には周囲を頼り、様々な機関や家庭、地域と連携をしていくことで、こどもたちにとってもより良い支援につながります。
6.「特別扱い」ではなく「個別最適な支援」を
グレーゾーンのこどもたちの対応をしているときに周囲のこどもたちや保護者から、「あの子ばかり特別扱いしている」と言われることがあるかもしれません。しかし、支援とは“公平”ではなく“公正”であることが大切です。全員に同じ支援をすることではなく、それぞれが安心して過ごすために必要な個別最適な支援を届けることが目的です。
この考え方をこどもたちにも日頃から伝えることが大切になってきます。
「みんなが安心して学童で過ごせるように、それぞれに合ったやり方を考えているんだよ」や、「目が悪い子が眼鏡をつけることをズルイという人はいないよね。それと同じように、その子その子に必要なお手伝いをしているんだよ」などと話すことで、集団の中でも互いの違いや個性を理解し合う土壌が育ちます。
こうした文化が根づいている学童は、結果的にグレーゾーンの子だけでなく、すべてのこどもにとって居心地のよい場所になります。
まとめ
グレーゾーンの子供たちは、制度や支援の狭間に置かれやすい存在です。だからこそ、学童保育所がこどもたちの安全基地・適切な支援機関として機能することは社会的にも大きな意味を持ちます。
学童保育所・家庭・学校が連携し、情報を共有しながら共通認識を持ってこどもたちを見守り、支えていくことで、あたたかな支援の輪がどんどん広がっていきます。誰一人取りこぼさない居場所づくりを、ぜひ今日から、学童保育の現場を起点に始めていきましょう!
career consultant

キャリアアドバイザーに
直接相談しませんか?
多数の求人の特徴や情報を熟知している担当者に直接ご相談していただくことが可能です!
お気軽にご利用ください。